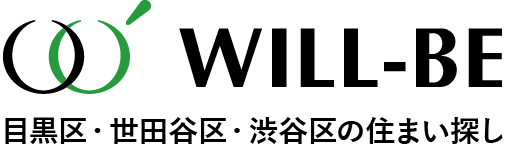相続や共同購入で注意!不動産の「共有トラブル」と解決策
- 家を買う
共有とは?
不動産の「共有」とは、ひとつの土地や建物を複数人で所有することをいいます。日本の法律では物理的に区切るのではなく、「持分」という割合で権利を分け合う仕組みになっています。
たとえば夫婦であれば2分の1ずつ、親族が出資すれば「本人が10分の9、祖父が10分の1」といった形になります。相続で母が2分の1、姉と弟がそれぞれ4分の1と分かれるケースもあります。このように、購入や相続の事情によって自然に「共有状態」が生まれることは珍しくありません。
共有不動産で起こりやすいトラブル
共有にはメリットもありますが、実際にはトラブルの原因になることも多いです。
たとえば売却する場合、たとえ1%の持分でも同意がなければ手続きは進みません。親族間で意見が割れ、時間だけが過ぎてしまうこともあります。さらに、共有者が認知症や事故などで意思表示できなくなると、手続きそのものが止まってしまいます。持分の譲渡や贈与によって思わぬ税金が発生することもあるので注意が必要です。
整理すると、代表的なトラブルは次のようなものです。
- 全員の同意がなければ処分できない
- 意見がまとまらず、解決に時間がかかる
- 意思表示できない共有者がいると手続きが止まる
- 税務上の予想外の負担が発生することがある
解決のために取れる方法
共有状態を整理するにはいくつか方法があります。
たとえば持分を買い取って単独所有にしたり、不動産そのものを売却して代金を分け合う方法です。場合によっては持分を贈与・放棄したり、遺産分割協議で調整することも考えられます。将来の相続を見据えて遺言書を作成しておくのも有効です。
代表的な解決策としては、
- 持分を買い取って単独所有にする
- 不動産を売却し、代金を分配する
- 贈与や放棄、遺産分割協議で整理する
- 遺言書を残して将来の共有を避ける
といった選択肢があります。

トラブルを避けるために
共有問題を未然に防ぐには、家族や関係者の間でしっかり話し合い、合意を形成しておくことが大切です。
さらに、税務上のリスクを確認しておくことも欠かせません。判断に迷う場合は、弁護士や税理士、不動産会社など専門家へ早めに相談することをおすすめします。
まとめ
不動産の共有は相続や共同購入でよくあることですが、処分や管理の場面で大きなハードルとなることがあります。「後でなんとかなる」と先送りにすると、いざという時に動けなくなるケースも少なくありません。
早めに整理しておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。もし共有不動産についてお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。