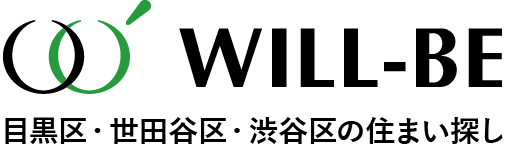賃貸経営における気候リスク対策
- 賃貸管理
猛暑・集中豪雨・水害にどう備えるか
近年、地球温暖化の影響により、日本各地で猛暑や集中豪雨といった異常気象が常態化しています。こうした気候の急激な変化は、日々の暮らしだけでなく、賃貸経営にも大きな影響を及ぼしています。
例えば、真夏の酷暑ではエアコンの稼働時間が長時間におよび、古い機種や性能の劣った設備は故障が頻発します。入居者からの緊急連絡や修理依頼が急増する中で、対応が遅れれば、「暑くて住めない」「管理がずさん」などのクレームや退去につながる可能性も否定できません。さらに、機器の調達が集中する時期には、交換品の納品が遅れたり、取り付け業者のスケジュールが取れず、対応に時間がかかるケースもあります。
一方、夏場のゲリラ豪雨や台風に伴う集中豪雨では、排水処理能力を超える雨量が一気に流入し、浸水被害や下水の逆流などのトラブルが発生するリスクも高まります。こうした水害は建物の構造体や内装を傷めるだけでなく、入居者の生活環境にも大きく影響し、長期的には退去や損害賠償といった法的リスクへと発展するおそれもあります。
建物の環境対策がオーナーの責務に
これらのリスクに対応するには、管理会社任せにせず、オーナー様ご自身による建物の「気候リスク対策」への意識と準備が不可欠です。物件の資産価値を守るためにも、できるところから対策を講じていくことが重要です。
たとえば猛暑対策では、以下のような建物仕様の改善が効果的です。
- 断熱材の強化(屋根裏・外壁など)
- 内窓(二重サッシ)の設置による断熱・遮熱性能の向上
- 樹脂サッシへの交換で気密性・遮音性も強化
- 窓の外側に日よけ(庇やすだれ、遮熱フィルム)を設置
これらの工夫により、冷房効率が上がるだけでなく、室内温度の上昇が抑えられ、入居者の快適性も高まります。
また、水害に対しては以下のような備えが有効です。
- 1階のコンセントや電源機器を床から高い位置に設置
- 室外機のかさ上げ
- 玄関や駐車場まわりの排水勾配の見直し
- 床仕上げをフローリングではなく防水性の高いコンクリートやタイルに変更
- 排水管の逆流防止弁の設置
こうした施工は、新築時でなくても、修繕・リフォームのタイミングで順次取り入れることが可能です。特に築年数の経過した物件では、これらの対策を講じることで、他物件との差別化や空室対策にもつながります。
賃貸経営の「見えないコスト」を減らすために
気候リスクへの備えは、「今すぐ目に見える利益」ではなく、中長期的な資産保全とリスク低減策としての意味を持ちます。たとえばエアコンの故障一つをとっても、真夏のピーク時に故障・交換となれば、以下のようなコストが見え隠れします。
- 入居者への対応に追われる管理会社の業務逼迫
- 部材の在庫不足・納品遅延による対応の長期化
- 入居者からのクレーム増加や悪評価の投稿リスク
- 設備不満による退去と空室期間の発生
- オーナー負担での設備更新(緊急手配で割高になることも)

つまり、故障してからの対応は「手遅れ」になるケースが多く、対応が遅れるほどコストもリスクも大きくなるのです。定期的な点検・計画的な交換を前提としたメンテナンスは、トラブルの予防につながるだけでなく、入居者の安心にもつながります。
ウィル・ビーの取り組みとご案内
ウィル・ビーでは、近年の気候変動リスクを見据え、主に使用期間が10年を超えるエアコンについては早めの交換を推奨しております。
特に7月〜9月はエアコン関連の修理依頼や交換依頼が非常に多くなるため、ピーク前の春頃から準備されることをおすすめしております。
また、物件ごとの立地や構造に応じて、以下のような気候対策も個別にご提案しております。
- 水害の可能性がある地域の排水・排水口対策
- 断熱性能が不足している物件への施工提案
- 外構周りや共用部における浸水・風害の備え
- 保険の見直しや補償内容の確認サポート
どの物件も状況はさまざまであり、一律の対策ではなく、「その物件に必要な対策」を適切なタイミングで講じることが大切です。ご不明な点や、ご自宅・所有物件について気になる点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。