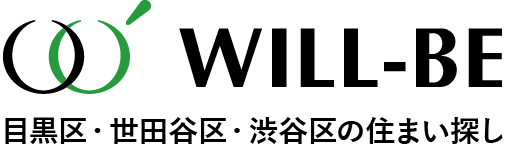これからの建物管理、押さえるべき3つの変化
- 賃貸管理
今押さえるべき管理オーナーの最新動向
近年、建物管理や改修に関する法律・規制が大きく変化しています。特にアスベスト調査や照明設備、太陽光発電に関する動きは、今後の物件管理に直接影響する重要ポイントです。今回は、管理オーナーとして知っておきたい最新動向を整理しました。
1. アスベスト事前調査の義務拡大(大気汚染防止法)
2023年10月より、建物の改修・解体工事において、延床面積に関わらずアスベスト調査結果の報告が義務化されました。対象は梁・躯体など構造耐力上主要な部分だけでなく、クロスやボード、床材、天井材などの内装仕上げ材も含まれます。これまで一部の大規模建物や改修工事のみが対象でしたが、現在はすべての建物に拡大されているため、スケルトンリフォームなどの工事でも事前調査が必須です。
さらに2025年以降は電子報告システム「石綿事前調査結果報告システム」を通じた報告が原則となり、届出内容の正確性や専門調査者の関与も厳格に審査される見込みです。
管理オーナーとしては、事前調査を怠ると行政指導や工事差し止め、損害賠償リスクにつながるため、早めに計画に組み込むことが重要です。
2. 2027年までに蛍光灯の生産・輸出入が完全停止
環境保護や輸入規制(RoHS指令、水俣条約など)の影響で、国内主要メーカーは2027年を目処に蛍光灯の生産・輸出入を完全に停止します。これにより、既存の蛍光灯器具は交換用ランプが手に入らなくなる可能性があります。
特に共用部やテナント照明で蛍光灯を使用している物件では、交換ランプの在庫がなくなった時点で照明切れによる施設運営の影響や、LED化工事が集中することで工事費の上昇が懸念されます。
管理オーナーとしては、早めに物件ごとに蛍光灯の使用状況を把握し、段階的にLED化計画を立てることがコスト抑制と入居者満足維持につながります。

3. 2027年、太陽光発電の設置義務化が本格化
省エネ法改正により、屋根置き太陽光パネルの設置義務や設置状況の報告が本格的に義務化されます。これまで努力義務とされていた導入も、気候変動問題の深刻化や省エネルギー政策の強化に伴い、実質的な義務化が進んでいます。
東京都では2025年4月から、新築住宅に対して年間供給延床面積基準に応じた設置義務が導入されています。今後は既存住宅や改修物件にも影響が広がる可能性が高く、管理オーナーは設備設置の可否や費用試算、補助金活用の検討が必要です。
太陽光発電の導入は、光熱費削減だけでなく資産価値向上や入居者募集のアピールポイントにもなるため、早めの検討が重要です。
資産価値を守るための次の一手
今後数年間で、建物管理に関する法規制や設備対応の重要性はますます高まります。管理オーナーとしては、早めに対応方針を検討し、適切な改修や設備更新を進めることが資産価値維持の鍵となります。
最新の動向を押さえ、計画的な管理を心がけましょう。