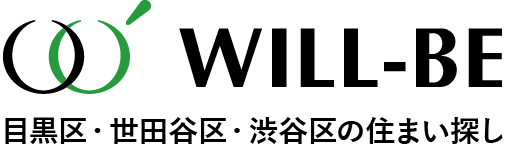家を売る前に知りたい!「4号特例」改正のポイント
- 売却
「4号特例」とは?改正の背景
「4号特例」とは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する小規模な建築物(例:木造2階建て、延床面積500㎡以下など)について、設計・工事が建築士によって行われていれば、構造計算書などの一部審査を省略できる制度です。
しかし、耐震性能や省エネ性能の確保の観点から、こうした審査省略制度が安全性・性能面で課題となっていました。加えて、熊本地震など大規模地震の教訓もあり、構造計算や審査の強化が必要とされました。
2025年4月からどう変わるのか?
1. 建築物の分類が変更される
- 新2号建築物:木造2階建てまたは延床200㎡超の建築物。従来の4号特例の対象外となり、構造計算書や省エネ関連書類の提出、建築確認申請・検査が義務化。
- 新3号建築物:延床200㎡以下の平屋。4号特例の審査省略制度が引き続き適用可能。
2. 着工までの時間・コストが増加
新2号建築物に該当する住宅では、構造計算や省エネ適合審査などが必要となり、設計・審査・工期が長引き、費用負担も増加する傾向があります。
3. 大規模リフォームも確認申請が必要
これまでは4号特例の下で大規模リフォーム(例:屋根・外壁の全面改修、柱・梁の過半数交換など)は確認申請不要でしたが、改正後はこれらにも確認申請が必要になることがあります。
戸建所有者が売却時に注意すべきポイント
① 建築確認済証・検査済証などの書類の有無を確認
書類が残っていない場合、不動産業者や建築士、市区町村窓口を通じて再建築可否を調査しておくことが重要です。
② 説明責任がより重要に
買主が「建て替えできると思っていた」「リフォーム可能と思っていた」と認識すると、後にトラブルになる可能性があります。
新2号建築物に該当する場合や、制限がある場合は、重要事項説明でも詳細に伝え、契約書にも特約として記載しておくことが望ましいです。
③ 契約書に特約を設けておく
買例えば「現状有姿で引き渡し」「売主は再建築不可に関して責任を負わない」などの内容を明文化するのが有効です。
④ 古家付き土地の場合の追加注意点
- 境界線の明示:境界が曖昧なままだと買主が不安となり、売却が難航します。測量士による事前測量が推奨されます。
- 残置物の処理:家具・家電・生活ゴミ等は売主負担で処分しておく必要があります。しない場合、買主の値下げ交渉や契約破棄リスクになります。
⑤ 小規模なリフォームは現行通り可能な場合も
主要構造部に関わらない内装や設備交換など、小規模な工事であれば、確認申請不要となる可能性があります(例:床面積200㎡以下の木造平屋など)。
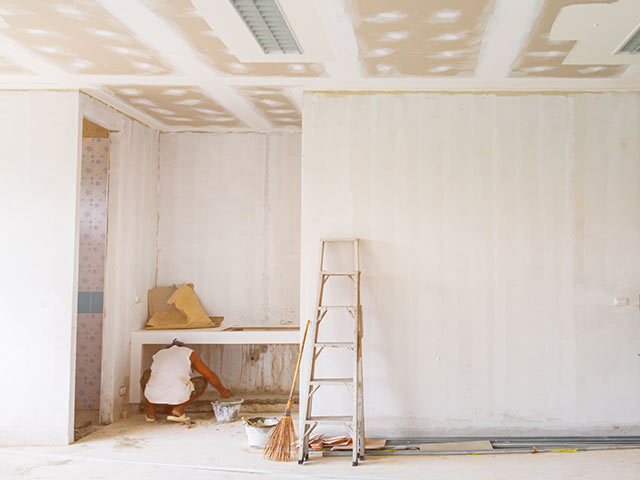
安心・スムーズな売却のために
2025年4月の建築基準法改正により、これまで審査が省略できていた多くの戸建住宅で、構造・省エネ審査や確認申請が必要となります。
これに伴い、売却時には書類の整備・説明責任の強化・契約内容の明確化などが不可欠です。特に古家付き土地や再建築不可物件では、事前調査と契約の工夫がスムーズな取引につながります。