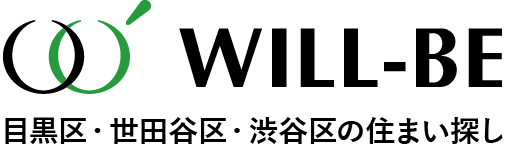親の認知症に備える不動産売却の事前準備
- 売却
高齢化社会で増える「親の認知症」と不動産売却の課題
高齢化が進む中、親の認知症は身近な問題となってきています。
不動産は資産価値が高く、売却には名義人本人の意思確認が不可欠です。そのため、判断能力が低下すると、売却のタイミングや条件に大きな影響を及ぼすことがあります。
今回は、親が認知症になる前にどのような準備をしておくべきかを、具体的な方法とともに整理します。
認知症が不動産取引に与える影響
不動産を売却するには、所有者本人の意思表示が必要です。しかし、認知症が進行すると、契約内容を理解・判断できないと見なされ、売買契約そのものが無効になる可能性があります。
仮に契約を締結しても、後に「判断能力がなかった」と争われると、買主とのトラブルや訴訟に発展するリスクもあります。そのため、認知症が進む前に、売却や資産管理の準備を整えておくことが極めて重要です。
成年後見制度の活用と注意点
判断能力が低下した後でも、家庭裁判所を通じて「成年後見制度」を利用すれば、後見人が財産の管理や売却を代行できます。
ただし、この制度には以下のような特徴と注意点があります
- 裁判所の許可が必要で手続きに時間がかかる
- 売却の自由度が制限され、柔軟な資産運用は難しい
- 後見人報酬などの費用負担が発生する
つまり、成年後見制度は最後の手段として考えるべきであり、親が判断能力を保っているうちに準備を進めることが望ましいといえます。

事前にできる準備
1. 任意後見契約の締結
元気なうちに「任意後見契約」を結んでおくことで、将来認知症になった場合でも、信頼できる親族や専門家が財産管理や売却を代行できます。成年後見制度より柔軟性が高く、契約内容も自由に設定できる点が大きなメリットです。
2. 家族信託(民事信託)の活用
近年注目されている手法が「家族信託」です。
親が元気なうちに不動産の管理権限を子どもや家族に信託することで、将来認知症になっても契約に基づき売却や運用が可能です。
裁判所の関与が不要で、自由度が高く、収益物件や将来売却を見据えた不動産に特に有効です。
3. 遺言書の作成
認知症によるリスクは売却だけでなく、相続時にも影響します。
不動産の分配方法を明確にしておく遺言書は、将来の家族間トラブルを回避するうえで不可欠です。
遺言が整備されていれば、売却や現金化もスムーズに進みます。
4. 資産整理と情報共有
不動産の登記簿謄本、固定資産税の納付書、権利証などの書類を整理し、家族間で共有しておくことも大切です。
売却時に「どの銀行に権利証があるのかわからない」といった状況は、手続きの遅延や余計な費用につながります。
事前に情報を整理しておくことで、売却や管理の効率も格段に上がります。
売却タイミングを見極める
親が高齢になると、「売却すべきか、保有を続けるか」という判断も必要です。
例えば、賃貸物件は収益が得られる一方、管理や修繕の負担が発生します。空き家の場合、固定資産税や維持費だけがかかり、放置すると資産価値の低下にもつながります。
親が元気なうちに、売却の方向性や今後の資産計画を家族で話し合うことが、後々の円滑な判断につながります。
家族でのコミュニケーションの重要性
最も重要なのは、親と子どもが率直に話し合うことです。
- もしものときにどうしたいか
- 不動産を売るか残すか
- 介護費用の備えはどうするか
こうした点を事前に共有することで、家族間のトラブルを回避できます。特にきょうだいが複数いる場合は、事前の合意形成が不可欠です。
専門家への相談
不動産売却には、法律・税務・登記など複数の専門知識が必要です。
司法書士、弁護士、税理士、不動産会社など、各分野の専門家に相談しながら進めることが、安心かつ最適な売却への近道となります。
特に、家族信託や任意後見契約は専門的知識がないと適切に設計できないため、早めに相談することが重要です。
親が元気なうちの準備が資産と家族を守る
親が認知症になってからでは、不動産の売却は制約が多くなります。成年後見制度を利用する手段はありますが、自由度やスピードに限界があります。そのため、親が元気なうちに家族信託や任意後見契約、遺言書の作成など、事前の準備を進めておくことが大切です。
さらに、家族間での話し合いや専門家のサポートを得ることで、資産を守りながら安心して将来に備えることができます。
不動産は「家族の生活」と「資産形成」の両面に直結する重要な財産です。親の意思を尊重しつつ、認知症に備えた準備を整えることが、家族全員の安心につながります。