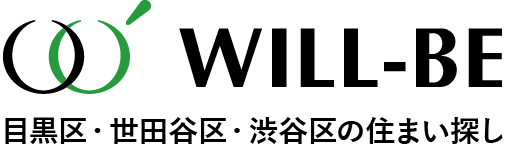都市型水害が増える今、オーナー様ができる「建物と入居者を守る備え」
- 賃貸管理
近年、ゲリラ豪雨や大型台風による被害が全国的に増えています。東京都内でも、短時間に激しい雨が降り、道路や住宅が冠水する「都市型水害」が頻発しています。都市部は舗装された地面が多く、雨水が地中にしみ込みにくいため、河川や下水道の処理能力を超えるとあっという間に水があふれてしまいます。
中でも世田谷区や目黒区は、川沿いの低地が多く、水害リスクが指摘されている地域です。世田谷区では多摩川や野川、目黒区では目黒川流域が浸水想定区域に含まれています。各区のハザードマップでも、想定される浸水深や避難経路が細かく示され、住民への注意喚起が行われています。
行政によるハード対策も進行中
東京都では、こうしたリスクに対応するために、下水道や河川の整備を進めています。
たとえば「目黒川流域」では、地下に雨水を一時的にためて流量を調整する荏原調節池や船入場調節池といった大規模施設が整備されています。荏原調節池は地下4層構造になっており、上部には都営住宅や福祉施設が併設されているなど、地域のインフラとしても活用されています。
また、世田谷区・目黒区の両区では、緊急用土のうステーションの設置も進められています。これは、区内の複数箇所に誰でも自由に持ち出して使える土のうを設置しておく取り組みで、大雨の際に一時的な浸水防止に役立ちます。
このように行政の対策も強化されていますが、実際の被害を最小限に抑えるには、オーナー様ご自身による備えも欠かせません。特に賃貸物件やマンションをお持ちの方にとっては、建物の被害が入居者の安全や資産価値に直結します。

賃貸オーナー様ができる水害対策
① 建物の浸水対策
駐車場やエントランスに止水板を設置
坂下や低地の物件では、短時間で水が流れ込むケースもあります。簡易型の止水板を用意しておくと、緊急時にすぐ対応できます。
電気設備・配電盤を1階以上に移設
浸水時に電気設備が壊れてしまうと、復旧に時間がかかります。建物改修の際に設置位置を見直しておくと安心です。
地下や半地下部分に逆流防止弁を設置
下水が逆流して室内にあふれる「内水氾濫」を防ぐために、排水口への逆流防止弁の設置が効果的です。
② 入居者への情報共有
「浸水リスクと避難ルート」をまとめて配布
物件ごとに周辺の避難所やハザードマップURLをまとめたシートを作っておくと、入居者の安心感が高まります。
緊急時の連絡体制を整備
災害時の連絡方法(LINE・メール・掲示板など)をあらかじめ明確にしておくと、いざという時にスムーズです。
③ 保険・資金面の備え
水害補償を含む火災保険の見直し
火災保険でも「水災補償」はオプション扱いのことがあります。地域のリスクに合わせて補償内容を再確認しておくと安心です。
修繕費用を見据えた積立金の確保
浸水被害の修繕費は想像以上に高額になることもあります。日ごろから少しずつでも備えておくことで、復旧がスムーズになります。
④ 日常管理の工夫
雨水マスや排水口の定期清掃
落ち葉やゴミが詰まると排水不良の原因になります。台風シーズン前に点検しておくことが大切です。
外構や植栽まわりの排水性を意識
透水性の高い素材を使った舗装や砂利敷きなども、雨水対策には効果的です。
「行政+オーナー」で、災害に強い住まいづくりを
行政の整備が進む一方で、オーナー様の自主的な取り組みも欠かせません。建物を守るための小さな工夫が、入居者の安全や信頼、そして資産価値を守ることにつながります。
いざという時に備えて、日常の点検や情報共有など、できることから少しずつ始めていきましょう。