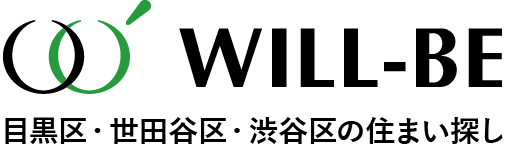令和7年度・東京路線価──全国を突き抜ける“一極集中”の勢い
- 売却
令和7年1月1日時点で公表された路線価(相続税評価額の基準)は、全国約32万地点の標準宅地で前年から+2.7%の上昇を記録。4年連続のプラス基調を維持しています。
中でも注目すべきは、東京都の伸び率が+8.1%と全国平均の約3倍に達したこと。まさに「一極集中」の勢いが加速している状況です。
地価上昇を支える“再開発”と“投資マネー”
東京都の地価がここまで上昇している背景には、海外からの投資マネーの流入と、再開発による都市部の魅力向上があります。特に、銀座・浅草・北千住といった駅前や観光地では、訪日観光客の増加や再開発事業が地価急騰を後押ししました。
40年連続トップの「銀座」──1㎡あたり4,808万円
全国最高路線価を記録したのは、中央区銀座5丁目・銀座中央通り(鳩居堂前)。
令和7年の価格は1㎡あたり4,808万円となり、前年から+8.7%の上昇。
40年連続で全国トップという圧倒的な存在感を誇っています。そのほか、渋谷・新宿・有楽町など、都心主要エリアも依然として高水準を維持しています。
上昇率が高かった注目エリア
変動率の大きかった地点として、以下のような再開発エリアが上位にランクインしました。
| 地点 | 前年比上昇率 |
|---|---|
| 浅草・雷門通り | +29.0% |
| 北千住西口駅前 | +26.0% |
| 中野駅北口駅前 | +24.7% |
これらの地域はいずれも、観光・再開発・利便性の向上といった要素が地価の押し上げ要因となっています。

“恩恵”と“副作用”──資産価値の増加と税負担の現実
このような地価の高騰は、土地所有者にとっては資産価値が増す恩恵をもたらします。
一方で、相続税評価額の上昇につながるため、税負担が増えるリスクも無視できません。「地価が上がる=資産が増える」という単純な図式では済まされない時代に突入しているのです。
相続・贈与を視野に入れる際には、計画的な資産対策と税務対応がますます重要になってきています。
いま求められる“出口戦略”
さらに、地価上昇が続く東京圏では、相続税対策だけでなく、資産流動化の視点も欠かせません。
- 土地の一部を売却して現金化する
- 建物を建てて賃貸収入を得る
- 家族信託などを活用して資産を保全する
といった、多様な選択肢を検討する動きが広がっています。
“バブル”への警戒と冷静な対応も必要
地価高騰を歓迎する一方で、価格乖離や一時的な観光需要のピークアウト、金融政策の転換(=金利上昇)といったリスクに警戒する声も高まっています。
都心部に需要が集中し過ぎることによる“逆回転”の可能性も視野に入れ、きめ細かな資産管理や出口戦略の構築が不可欠な局面を迎えていると言えるでしょう。
まとめ
令和7年度の東京路線価は、全国平均を大きく上回る上昇を記録し、都市部への資金集中と再開発による地価押し上げの構図が一層鮮明になりました。特に観光・商業エリアを中心に高騰が目立ち、資産価値の増大という側面とともに、相続税負担や将来的な価格変動リスクといった課題も浮かび上がっています。
不動産を「持つこと」そのものが資産形成の鍵となる今、地価上昇をどう受け止め、どのように備え、活かすか──。所有者一人ひとりに求められるのは、時代の変化に即した冷静で柔軟な対応です。